産業廃棄物収集運搬と許可について

こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っ […]
More
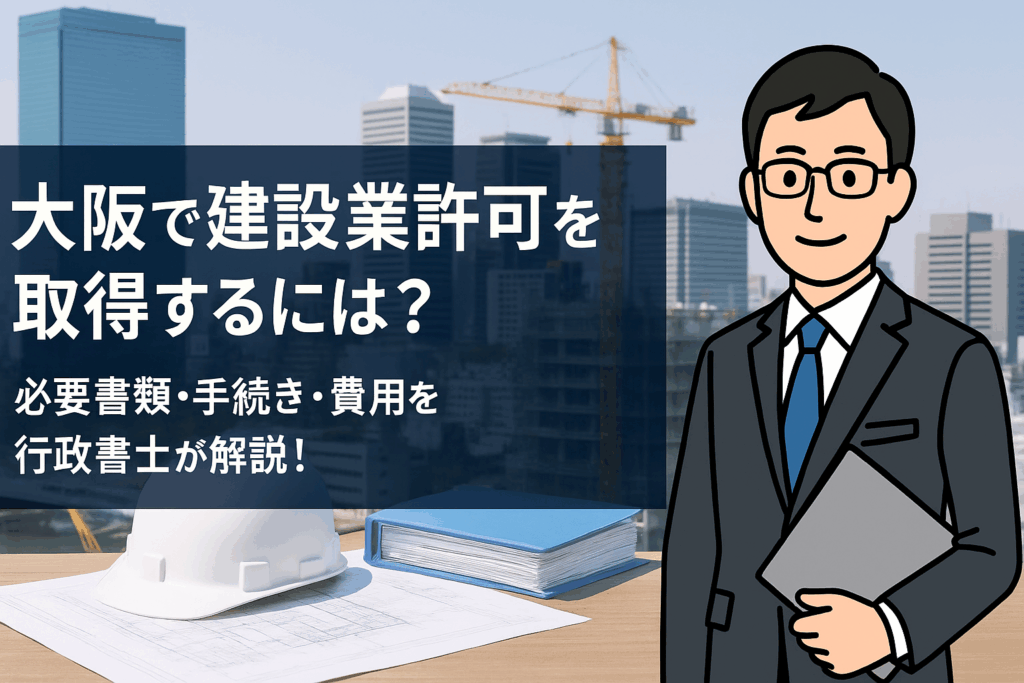
大阪で建設業を始めるには、まず「建設業許可」を取得することが重要です。許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がり、元請け企業や公共工事からの信頼も得やすくなります。とはいえ、必要書類の準備や申請手続きには専門的な知識が求められ、初めての方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
本記事では、大阪で建設業許可を取得するための基本的な流れや必要な書類、費用の目安までを行政書士がわかりやすく解説します。スムーズな許可取得のために、ぜひ参考にしてください。
目次
建設業許可とは、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合に、国または都道府県から受けなければならない許可制度のことで、建設業法に基づき、この許可が必要となります。
建設業法第3条では、「建設工事の完成を請け負う営業を営もうとする者は、元請・下請を問わず、原則として建設業許可を受けなければならない」と規定されています。ただし、軽微な工事(小規模なリフォームなど)の場合には、許可を受けずに営業することも可能です。以下で詳しく説明します。
建設業許可が必要となるのは、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合です(建設業法施行令第1条の2より)。
建築一式工事:工事1件の請負金額が1,500万円以上(木造住宅の場合は1,500万円または延べ面積150㎡以上)
建築一式以外の工事:工事1件の請負金額が500万円以上(消費税を含む)
たとえば、内装工事会社が600万円の店舗改装工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。逆に、480万円の修繕工事であれば、許可がなくても違法にはなりません。
また、建設業許可は「元請」だけでなく「下請」業者にも適用されます。たとえ下請であっても、上記の金額を超える工事を請け負えば、許可が必要となります。
建設業許可には、大きく分けて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
一般建設業許可は、500万円以上(税込)の工事を行う場合に必要になる許可です。ただし、建築一式工事については、1,500万円以上となります。小規模から中規模の工事を中心に請け負う業者が対象となります。
特定建設業許可は、1件あたり4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合に必要な許可です。大規模な工事を請け負う元請業者が取得する必要があります。
また、特定建設業許可を取得するためには、一般許可に比べて厳しい財務要件や経営業務の管理責任者に関する要件が課されます。これにより、下請業者への支払い能力や信用力を担保する目的があります。
建設業許可が必要な工事を無許可で行った場合、建設業法に基づき、以下のような罰則が科される可能性があります。
無許可営業の罰則
懲役3年以下または罰金300万円以下
法人の場合は代表者や役員なども処罰の対象となる可能性があります。
このように、許可を得ていない状態で営業を続けることは、法的なリスクに加え、会社の信用を大きく損なう要因となります。
【事例】大阪府での行政指導
たとえば、大阪府では、無許可で工事を行っていた事業者に対して立入検査・是正指導を行う事例もあり、最悪の場合は営業停止命令や告発につながることもあります。
建設業許可は、一定の規模以上の工事を行う上で不可欠な要件です。無許可営業は重大な法令違反となり、会社の将来を左右しかねません。とくに大阪など都市部では、元請・下請ともに法令遵守への意識が高まっており、許可取得の有無が取引の判断基準となるケースも少なくありません。
行政書士としては、許可の取得だけでなく、その後の更新や業種追加、変更届などの継続的な手続きも一括して支援が可能です。適切なタイミングで、確実に許可を取得し、安心して建設業を営んでいくためにも、まずは一度専門家にご相談されることをおすすめします。


建設業許可を取得するには、建設業法で定められた基本的要件を満たす必要があります。大阪府での申請もこの全国共通の基準に基づいて審査が行われます。
行政書士としては、単に申請書を整えるだけではなく、各要件を客観的に証明する資料の収集や整理、場合によっては補足説明の準備も含めてサポートします。
まず1つ目の要件が「経営業務の管理責任者(経管)」の設置です。
これは、許可を申請する法人または個人事業主が過去5年以上にわたって建設業の経営業務を適切に行っていた経験を持つことが求められます。令和2年10月の建設業法改正により、経験の要件が緩和され、「補佐経験(副社長や取締役など)」でも認められる場合があります。
【具体例】
大阪府では、過去の履歴事項全部証明書、工事請負契約書、決算報告書などを通じて、客観的な立証が求められます。
2つ目は、「専任技術者」の配置です。
申請する業種ごとに、一定の実務経験や資格を持つ技術者を、営業所に常勤かつ専任で配置する必要があります。
【要件の一例】
実務経験:該当業種に関し10年以上の経験
有資格者:一級施工管理技士、建築士など
大阪で許可を取る際は一定の資格を証明する書類や実務経験の証明書類(工事の請求書等)を準備する必要があります。また、実務経験では取得できない業種もありますので、大阪府の建設業許可申請の手引きなどで十分に確認しておく必要があります。
3つ目は、事業を継続的に行えるだけの「財産的基礎」があるかどうかです。
【一般建設業の要件】
下記のどちらかを満たす必要があります。
を証明できること
【特定建設業の要件】
直前の決算期における財務諸表において、下記のすべてを満たす必要があります。
この自己資本額は、直近の決算書や預金残高証明書などで証明します。資本金を増資することで対応するケースもあり、行政書士と税理士が連携して支援することも可能です。
最後に、「欠格要件」に該当する場合、いかに他の条件を満たしていても許可を取得することはできません。
【代表的な欠格要件】
ここでは代表的なものを列挙しております。大阪府では、過去の行政処分歴、登記情報、暴力団排除条例に基づいた誓約書の提出などが求められます。
その他にも、法人であれば社会保険に加入していることを必ず証明する必要があったり、営業所が要件を満たしているかの確認等もありますので、詳細については大阪府の建設業許可申請の手引きを確認するか、お近くの行政書士にお問い合わせください。

建設業許可の取得は、単なる書類提出ではなく、要件確認から資料収集、提出、審査まで一連の流れがあります。大阪府では、全国共通の基準に基づきながらも、都道府県毎で異なる運用や受付方法があるため、事前の準備と確認が非常に重要です。
以下では、建設業許可の「必要書類」「申請の流れ」「提出先・受付方法」「許可までの期間」について、大阪府の最新情報に基づき解説します。
建設業許可申請で求められる書類は、個人か法人か、また新規・更新・業種追加などの申請区分によって異なりますが、大阪府への新規申請(一般建設業・法人)の場合、おおむね以下のような書類が必要です。
主な必要書類
※最新の様式や記載例は大阪府の公式ホームページ「大阪府/建設業許可の申請手続き」に掲載されています。
申請の全体の流れを把握することで、スムーズな準備が可能になります。以下に、申請手続きの一般的な流れと、行政書士が関わるポイントを示します。
大阪府の建設業許可申請は、大阪府咲洲庁舎(大阪市住之江区)にある建築振興課が窓口となっています。
【提出先】
大阪府 都市整備部 建築振興課 建設業担当
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号(咲洲庁舎)
【受付方法】
建設業許可申請は窓口受付のみで、郵送や電子申請は不可
入口で受付をすると番号が発行されますので、呼ばれるまで待機
行政書士による代理提出が一般的
【受付時間】
平日9:30~17:00(土日祝除く)
日によっては、窓口が非常に混みあっていますので、窓口には早めに行くことをオススメします。
※詳細は「大阪府/建設業許可窓口案内」をご確認ください。
申請から許可が下りるまでの標準的な審査期間は以下の通りです。
【大阪府での標準処理期間】
申請書を受付した日から、許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は土日、祝日を含む30日
ただし、書類不備や追加資料の提出があると、審査が一時中断され、期間が延びる可能性があります。
【行政書士の視点】
経験上、窓口が平日しか開いていないため、建設業者の方が自身で申請される場合、不備等があると2~3か月以上かかってしまうケースも珍しくありません。行政書士に依頼した場合、最短で申請から約1か月ほどで許可取得に至るケースも多くあります。
建設業許可の申請は、「書類を出せば通る」ものではなく、要件の裏付けを客観的資料で立証する作業です。大阪府では年間多数の申請があり、厳格な審査が行われているため、書類不備や記載ミスによる再提出も珍しくありません。
行政書士に依頼することで、要件の精査、資料の準備、記載ミスの防止など、手間と時間を大きく削減できます。特に初めて申請される方は、まず専門家に相談することを強くおすすめします。
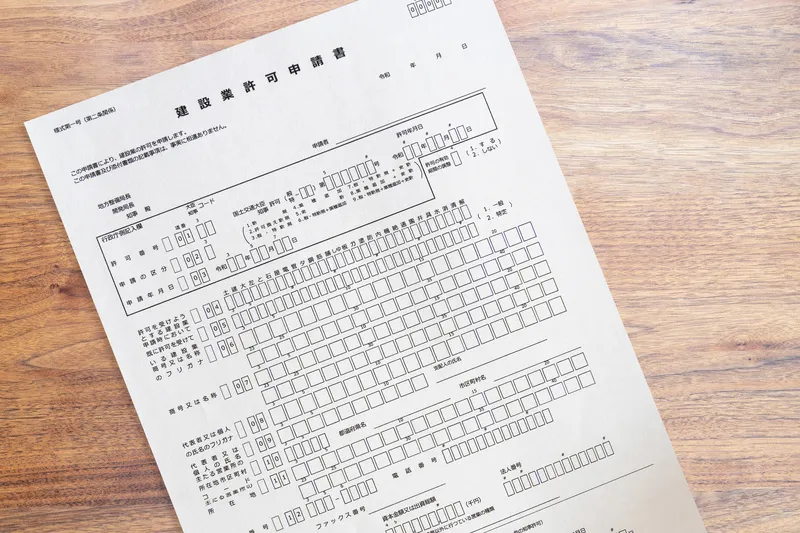
建設業許可を取得するためには、申請手数料(法定費用)と、行政書士への依頼費用がかかります。申請者がどれくらいの費用を見込んで準備すべきか、具体的な金額とともに解説します。
建設業許可の申請には、法定費用として所定の手数料が必要です。
【大阪府の新規許可申請手数料】
一般建設業又は特定建設行許可:90,000円
これらの手数料は、申請書類の提出時に現金またはクレジットカードで支払う必要があります。
建設業許可の申請を行政書士に依頼する場合の費用は、以下の要因に基づいて変動します。相場としては、業務の内容や申請の種類、申請者の事業規模などによって異なります。
【一般的な費用相場】(税込み)
新規申請(一般建設業許可):121,000円~165,000円
新規申請(特定建設業許可):143,000円~220,000円
更新申請:88,000円~132,000円
業種追加申請:99,000円~143,000円
この費用の他に証明書類の取得(履歴事項全部証明、登記されていないことの証明など)費として3,000円~5,000円がかかります。
【実例】
例えば、大阪府で一般建設業許可を新規で申請する場合、行政書士の依頼費用は121,000円から165,000円程度となります。この費用は、業種や申請者の個別の状況によって増減します。
また、特定建設業許可の新規申請は、要件が厳格なため、比較的高額となり、143,000円以上を見込んでおくと良いでしょう。

| 業務内容 | 報酬(税込) | 印紙代金・備考 |
|---|---|---|
| 建設業新規許可申請(知事) | 132,000円〜 | 90,000円 |
| 建設業新規許可申請(大臣) | 165,000円〜 | 150,000円 |
| 建設業許可更新(知事) | 88,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可更新(大臣) | 110,000円〜 | 50,000円 |
| 建設業許可業種追加申請 | 88,000円〜 | 50,000円 |
| 決算変更届(1期) | 33,000円〜 | |
| 経営事項審査申請 | 165,000円〜 | 23,000円 (規模、業種により多少変動) |
| 入札参加資格審査申請 | 33,000円〜 | 1箇所あたり |
| 変更届 | 33,000円〜 |

建設業許可申請は、単に必要書類を提出するだけではなく、法的要件を満たしていることを証明するための慎重な準備と手続きが求められます。特に初めて申請を行う場合や、要件が複雑な場合には、行政書士に依頼することが非常に効果的です。以下では、行政書士に依頼することで得られるメリットを具体的に紹介します。
建設業許可申請には多くの書類が必要であり、さらにその書類が法律に基づいた形式で整っているかを確認する必要があります。申請者自身で進める場合、要件の見落としや書類作成のミス及び不備が発生しやすく、結果的に申請が遅延したり、不許可となるリスクが高まります。
【メリット】
行政書士に依頼することで、申請に必要な書類が正確に作成され、要件に沿った証明が行われます。これにより、申請者は書類作成の負担から解放され、安心して申請を進めることができます。
また、行政書士は申請要件に基づき、必要な証明書類(納税証明書、履歴事項全部証明書など)を正確に収集・整理するプロフェッショナルです。例えば、過去の実績や事業内容に基づく証明を求められる場合でも、必要書類の手配を迅速に行います。
建設業許可の申請において、最も重要な点は要件を正確に満たしているかどうかです。特に、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者に関する証明、財産的基礎など、細かな要件を満たしているかの確認は専門知識を要します。
【メリット】
行政書士は、要件の確認作業や申請書の精査を行う専門家です。過去の申請事例や、行政機関の最新の運用に基づいて、不許可となるリスクを最小限に抑えるためのチェックを徹底的に行います。例えば、大阪府での申請時においても、行政書士は不許可となる原因となり得る小さな不備を見逃さずに修正を提案します。
実際、建設業者の方が自身で申請したが修正に対応することが困難となり、行政書士に依頼されるケースもあります。申請内容に少しでも不安がある場合は専門家による事前チェックが役立ちます。
建設業許可の申請は、申請書提出だけで終わりではなく、その後の許可取得後の運用や更新手続きも重要です。特に事業の成長に伴い、公共工事を受注するための経営事項審査を依頼するというケースもあります。その際、新規許可申請の時から経営事項審査に必要なアドバイスを行ってもらえることもあります。
【メリット】
行政書士に依頼すれば、申請後のサポートも手厚いのが特徴です。例えば、許可取得後に必要な更新手続きや、業種追加申請などもサポートします。また、許可を取得した後に必要となる法令の変更や新たな規定についても、行政書士は常に最新の情報を把握しており、適切なタイミングでの助言や対応が可能です。
【実例】
例えば、大阪府内で建設業許可を取得した後、業種追加申請や事業所変更申請を行う際には、行政書士がスムーズに手続きを代行します。これにより、事業者が許可を最大限に活用できるようサポートが続くため、長期的な運営の安心感が増します。

建設業許可に関して、申請を検討している方々からよく寄せられる質問をまとめました。以下の質問に対する回答を参考に、あなたの状況に応じた最適な判断をしてください。
個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。建設業許可は法人だけでなく、個人事業主にも適用されます。個人で事業を営む場合でも、許可を取得することによって、公共工事を受注することができるようになります。
【申請に必要な条件】
個人事業主が建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者:個人事業主が経営者として責任を持ち、事業を適切に運営していることを証明できること。
専任技術者:施工に必要な技術を持った専任技術者が確保されていること。
財産的基礎:一定の資産や収入があること。特に新規開業の場合は、事業資金をしっかり確保していることが重要です。
実際には、新たに開業したばかりの個人事業主が許可を取得するのは難易度が高いことがありますが、しっかり準備すれば問題なく申請できます。特に行政書士に依頼すると、必要書類の整備や要件確認がスムーズに進み、許可取得の確率が上がります。
建設業許可を取得した後も、決算変更届や更新手続き、業種追加、事業所変更などの手続きが必要です。これらの手続きは、許可を維持するために必ず行うべき重要な事項です。
【決算変更届】
法人の場合は、会社毎に定められた決算期に基づいて財務諸表等を作成して、毎年提出する必要があります。個人事業主であれば、毎年の確定申告が終わった後に財務諸表等を作成して提出が必要になります。注意事項として、提出するのは税理士等が作成した決算書ではなく、定められた財務諸表の様式で作成して提出する必要があることです。
【業種追加】
新たに必要な業種の許可を取得する場合は、業種追加の許可申請を行います。新規許可申請と同様に専任技術者の要件等をしっかりと確認して申請を行う必要があります。
【更新手続き】
建設業許可は、基本的に5年ごとに更新が必要です。更新手続きを行う際には、更新に必要な書類を提出し、要件を再確認する必要があります。更新申請の際も、前回の許可申請と同様に、事業内容や財務状況、技術者の配置などをチェックし、問題がなければ更新が認められます。期限切れとならないよう注意が必要です。期間の管理を行ってくれる行政書士もいますので、丸投げしてしまうのも一つです。
【変更手続き】
許可後の変更が必要な場合もあります。例えば、事業所の移転や専任技術者の追加などです。これらの変更が生じた際は速やかに変更手続きを行う必要があります。
【申請後のサポート】
行政書士に依頼しておくと、更新や変更手続きもスムーズに進めることができます。特に更新の際には、許可を維持するための手続きや期限をしっかり管理し、必要な書類を揃えて提出するサポートを行います。
当事務所が選ばれる
他とは違う6つの強み
行政書士くすき事務所はお客様がなんでも気軽に相談できる環境を目指し、「フットワーク軽め」「レスポンス早め」「愛想多め」「仕事まじめ」を合言葉に働いています。おかげさまで多くのお客様から喜びの声をいただいております。
当事務所は大阪メトロ四つ橋線なんば駅から徒歩5分の好立地。
その他各線なんば駅からも徒歩圏内です。お仕事帰りなどにも利用しやすい好アクセス!
大阪市内で開業後、多数のお客様から好評をいただいております。
豊富な取引実績は信頼の証。是非弊所におまかせください!ご満足いただけることを御約束いたします。
市場調査を定期的に行い、相場や適性価格を意識しております。市場と比較し高くなることはございませんのでご安心ください。
土日祝や、夜間帯でもお問い合わせには喜んでご対応いたします。
どんな些細なことでもお気軽にご連絡ください。
ご相談後しっかりとアフターフォローまで行います。
必ずお客様のご不明点を最後まで解決することをお約束致します。
電話かメールかラインで問い合わせ
(問い合わせ内容が間違っていても、全く問題ございません。
まずは、お気軽にご相談ください。)

直接面談かズームにて詳細をヒアリング

手順や報酬の確認

契約書や誓約書の締結
(必ず締結前に詳しくご説明致しますのでご安心ください!)

お支払い
(基本的に着金確認後の業務開始となります)

業務開始
(申請完了まで)

建設業許可は、事業者にとって重要なステップであり、専門的な知識と正確な手続きが求められます。大阪で建設業許可を取得する際は、行政書士に相談することが最も効率的で安全な方法です。専門家に依頼することで、書類作成から申請後のサポートまで、安心して許可取得を進めることができます。
もし、建設業許可について不安がある場合は、早めに行政書士に相談し、手続きを確実に進めましょう。専門家によるサポートで、あなたの事業も確実に成長を遂げることができます。